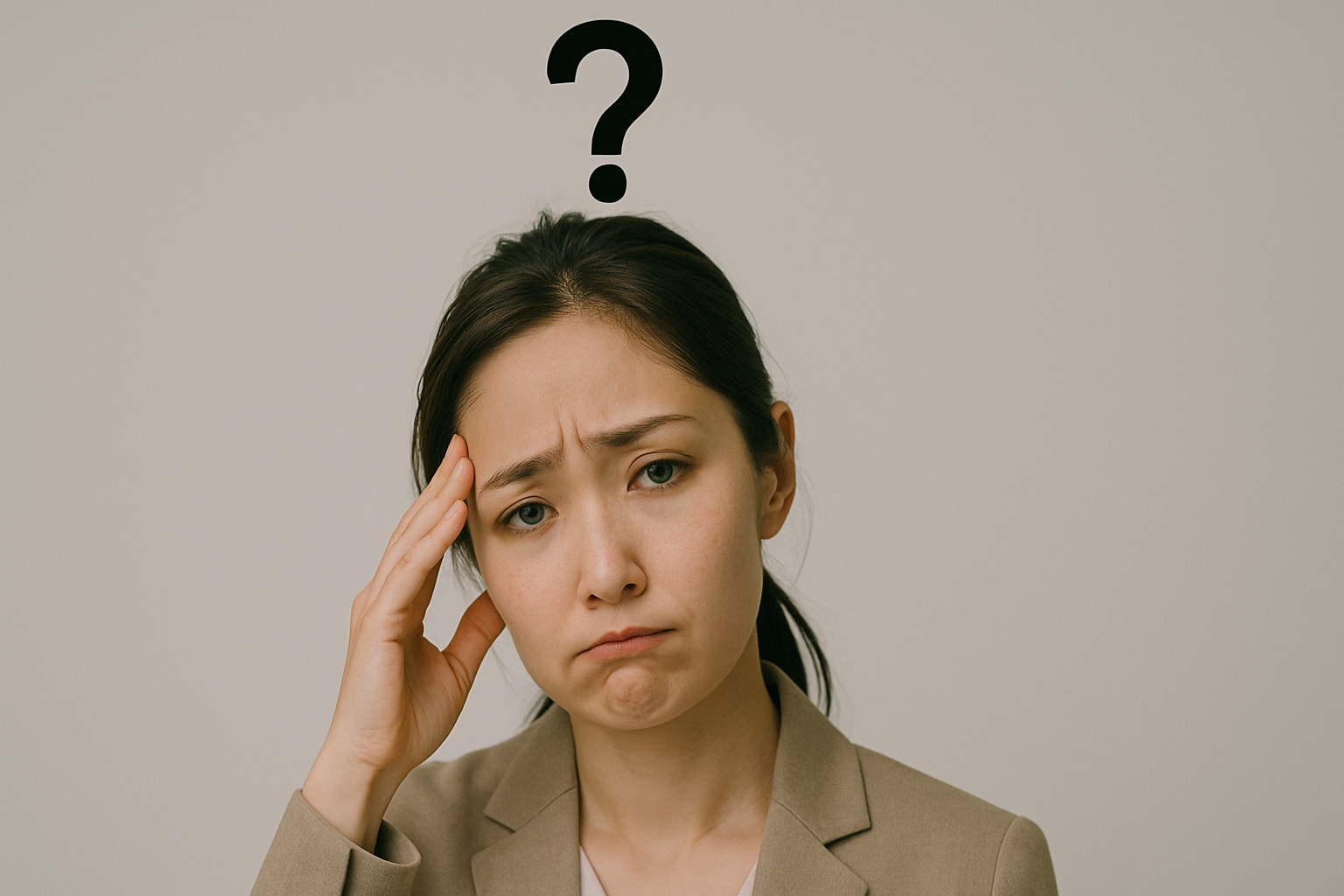言葉の行き違い
意図を正確に、誤解のないように相手に伝えるのは難しいものです。
ある会社では、各部門の代表者が集まり、業務改善について話し合うための会議を定期的に行なっています。ただし、今回は参加が強制ではなく、自由参加とすることになりました。
そこで会議の担当者は部下に「今回は自由参加にすると決まった」と伝え、案内文の作成を任せました。部下はその言葉を受けて、社内の掲示板に「関係者は自由にご参加ください」と書いた案内を掲載しました。
しかし、案内を読んだ従業員からは、「代表者が出ればいいのか?それとも全員が参加すべきなのか?」といった声が寄せられ、対応に混乱が生じました。「自由に参加」という表現が、人によって異なる解釈をもたらしたのです。
担当者は部下にもっと丁寧に説明すべきだったでしょう。また、部下も「自由参加」の意味を確認し、正確に伝わる案内を作成すべきでした。伝え方と受け取り方、どちらも大切なのです。
今日の心がけ◆相手の受け取り方を想像しましょう
出典:職場の教養7月号
感想
この話は、日常の中で誰もが経験しうる「言葉の行き違い」というテーマに焦点を当て、非常に実感を持って受け止めることができました。
特に、「自由参加」という一見明快な言葉でさえ、受け手によって解釈が異なるという現実は、多様な価値観や立場が混在する職場環境においては避けて通れない課題だと思います。
担当者と部下、それぞれが自分の役割をきちんと果たしながらも、思いがけず誤解を招いてしまうという展開に、人間関係や業務の難しさがにじみ出ていて興味深かったです。
また、「今日の心がけ」として提示された「相手の受け取り方を想像しましょう」という言葉には深く頷かされました。
伝える側が自分の意図だけでなく、相手の理解力や状況、立場を考慮して言葉を選ぶことの重要性がここには詰まっています。
相手の反応を想像し、誤解の余地を減らす工夫をすることが、信頼関係を築くうえでも極めて大切な姿勢だとあらためて感じました。
否定的な感想
この話には若干のもどかしさを感じました。
問題が起きた原因として、担当者や部下の不注意が指摘されていますが、それだけで本質を語り尽くせるのでしょうか。
「自由参加」という表現に対する明確な定義や、組織全体での共通理解が不足していた点こそが、より根深い問題ではなかったかと思います。
個人の責任に焦点を当てすぎているようにも見え、もう少し組織的な仕組みや文化の問題に目を向けてほしかったと感じました。
さらに、案内文を一人の部下に任せたまま内容の確認をせず掲示されたという流れには、基本的な業務フローの甘さが感じられ、そちらにも焦点が当たるべきではなかったかと思います。
「言葉の行き違い」という問題を個人のミスに還元してしまうと、再発防止には繋がりにくいようにも感じました。
伝える側と受け取る側の相互理解を大切にするのであれば、その前提となる組織内のコミュニケーションルールをどう築いていくかまで踏み込んで考えたいところです。
感想がいまいちピンとこない方は…
「なんかしっくりこないんだよなぁ」「でもなかなか思いつかない…」そんな時は、感想文ジェネレーターをお試しください。
あなたのお好みのテイスト・文字数で職場の教養の感想文を生成できます!