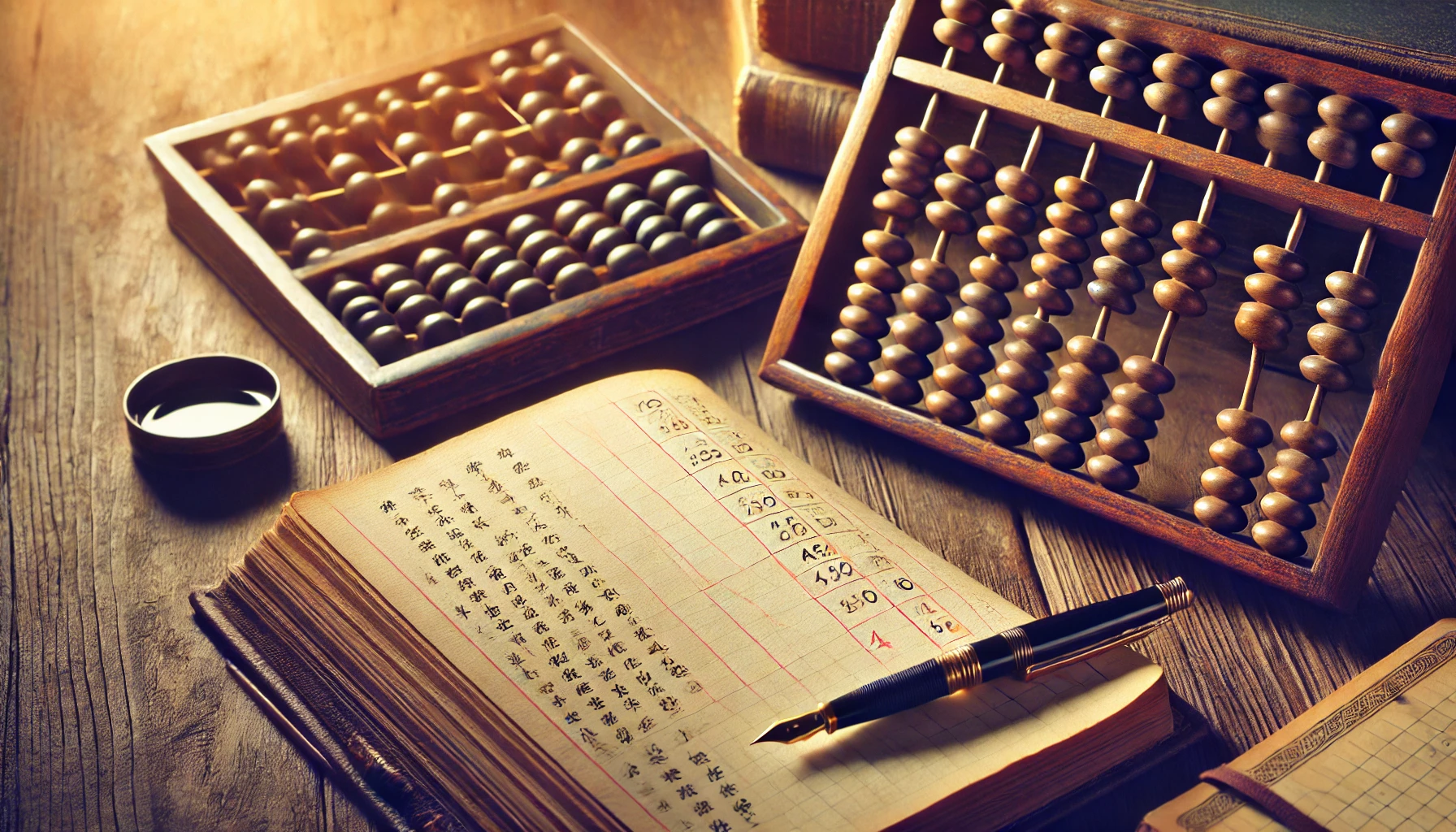道徳と経済
昨年、発行された新紙幣のデザインに選ばれた一人に渋沢栄一がいます。
渋沢栄一は「日本資本主義の父」と呼ばれ、五百もの企業の設立にかかわり、国の近代化に大きく貢献しました。さらに、約六百の教育機関や社会公共事業、研究機関の設立・支援にも尽力しています。
渋沢は「道徳経済合一」の思想でも知られ、このテーマで多くの講演を行ないました。企業の目的が利潤の追求にあっても、その根底には道徳が必要であり、国家や人類全体の繁栄に対して責任を持たなければならないと考えていたのです。
私たちが仕事に取り組む際の心構えについて考えてみましょう。金銭を得るために頑張ることは決して悪いことではありませんが、他者や公共の利益を考えることも大切でしょう。
私たちも、自分の利益だけにとらわれず、誰かの幸せを願って仕事に取り組むと、新たな視点が見えてくるかもしれません。
今一度、仕事に対する自身の心の軸を確認してみてはいかがでしょうか。
今日の心がけ◆他社を思って働きましょう
出典:職場の教養2月号
感想
渋沢栄一の「道徳経済合一」の思想を改めて考える機会を得られたことに、大きな意義を感じました。
資本主義の原則はしばしば利潤追求に重きを置かれがちですが、渋沢の考えは、それだけではなく「道徳」を経済の基盤とするべきだというものであり、これは現代社会にも通じる普遍的な価値観だと思います。
単なる利益追求ではなく、社会全体の発展や公共の利益を考える姿勢が、日本の経済発展を支えた大きな要因だったのでしょう。
特に、彼が設立や支援に関わった企業が五百、教育機関や社会公共事業が六百に及ぶという数字には驚かされます。
企業活動だけでなく、教育や社会事業にも精力的に取り組んだという点が、彼の「利己と利他の調和」を重視する姿勢をよく表しています。
現代においても、ビジネスの成功が単なる個人の利益だけではなく、社会全体の繁栄につながるように考え行動することが求められるはずです。
また、「私たちが仕事に取り組む際の心構えを考える」という視点の提示が非常に良いと思いました。
仕事をする理由は人それぞれですが、単に「お金を稼ぐため」だけではなく、「誰かの幸せにつながる仕事ができているか」という視点を持つことで、働く意味をより深く見つめ直すことができます。
短期的な利益だけを求めるのではなく、長期的に価値を生み出す働き方を意識することで、より充実した仕事ができるのではないでしょうか。
「今日の心がけ」の「他者を思って働きましょう」という言葉も、とても共感できます。
自分の利益だけを考えるのではなく、周りの人々や社会のために何ができるのかを考えることが、結果として自分自身の成長にもつながると思います。
こうした視点を持つことで、より豊かで充実した働き方ができるのではないでしょうか。
否定的な感想
渋沢栄一の「道徳経済合一」の考え方は素晴らしいものですが、実際の現代社会において、それをどこまで実践できるのかという点には疑問も感じました。
理想としては「道徳と経済の両立」が望ましいものの、現実には厳しい競争の中で利益を追求せざるを得ない状況が多く、道徳的な経営が必ずしも成功につながるとは限りません。
渋沢が活躍した時代と現代とでは、経済の構造も大きく異なっているため、単純に彼の理念を現代のビジネスに当てはめることは難しいでしょう。
また、渋沢の思想は一見すると「企業の社会的責任(CSR)」や「ステークホルダー資本主義」に通じるものですが、それでも現代の多くの企業では、結局のところ短期的な利益が優先されがちです。
例えば、企業が社会貢献活動を行うとしても、それが企業のブランディングやマーケティングの一環として利用されることが多く、純粋な道徳心から行われるケースは少ないのが現実です。
そうした中で、「道徳経済合一」を本当に実践できるのかという点には、疑問が残ります。
「私たちも、自分の利益だけにとらわれず、誰かの幸せを願って仕事に取り組むと、新たな視点が見えてくるかもしれません。」という部分には共感できるものの、それを実際にどう実践するのかという具体的な方法が示されていないのは少し物足りなさを感じました。
ただ「他者を思って働こう」と言われても、現実的には「どうやって?」という疑問が残ります。
例えば、企業であれば従業員の待遇改善や社会貢献活動の推進、個人であればボランティア活動や環境への配慮といった具体例を挙げることで、より実践的な内容になったのではないでしょうか。
「今日の心がけ」の「他者を思って働きましょう」は理想的な考え方ですが、それが具体的にどういう行動につながるのかを考えることも重要です。
ただ漠然と「道徳的であれ」と言われるのではなく、「どんな小さなことからでも始められるのか」といった視点が加わると、より実践しやすくなると思いました。
感想がいまいちピンとこない方は…
「なんかしっくりこないんだよなぁ」「でもなかなか思いつかない…」そんな時は、感想文ジェネレーターをお試しください。
お好みのテイスト・文字数で感想を生成できます!