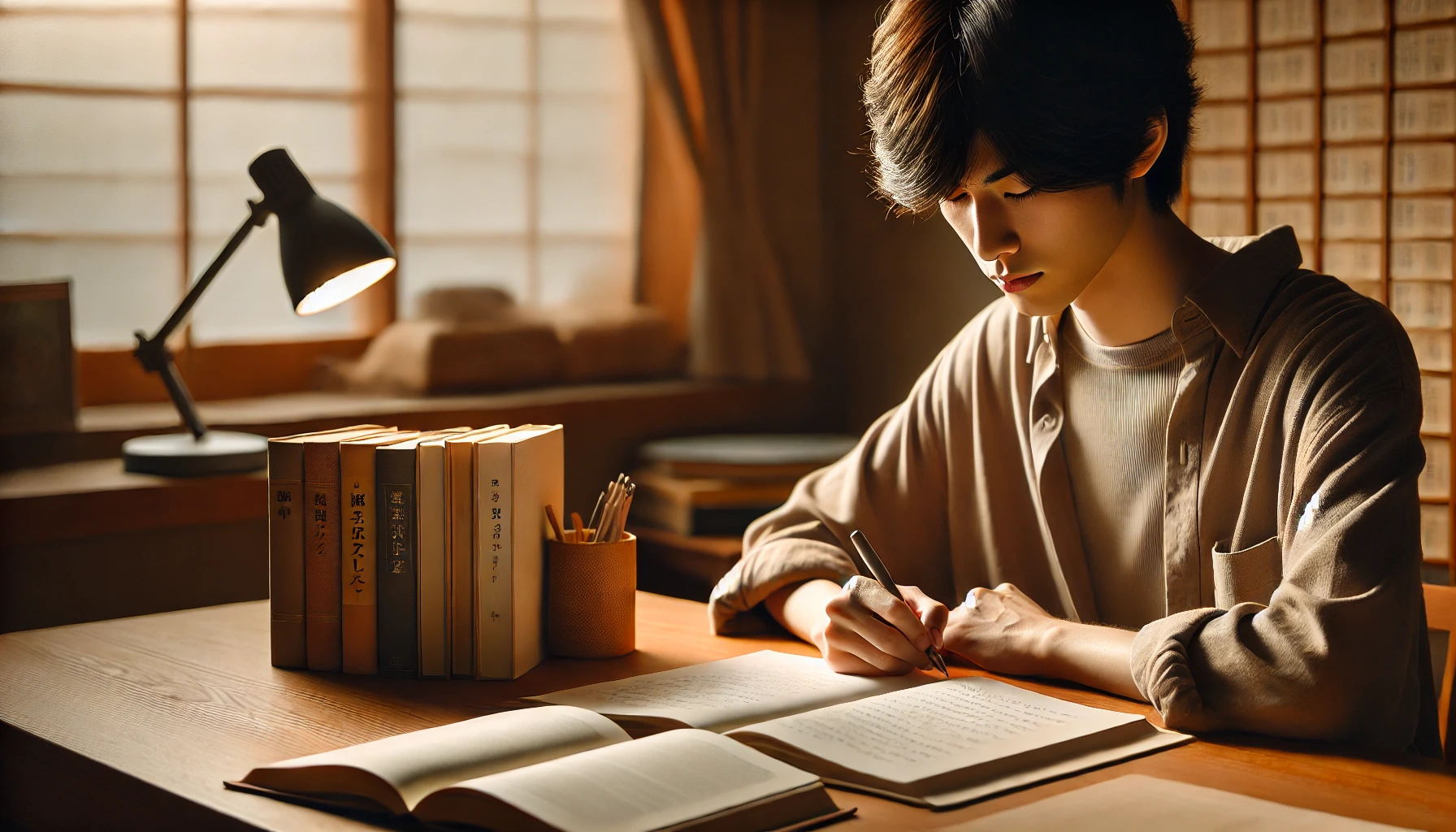日本語を学ぶ
日本語は、習得が難しい言語と言われます。
英語の表記はアルファベット二十六文字のみですが、日本語は、漢字に平仮名、カタカナがあり、縦書きと横書きがあります。さらに、漢字には様々な読み方があり、名前や地名などは、独自の読み方をするものも多数あります。
また、状況によって、尊敬語・謙譲語・丁寧語を使い分ける必要もあります。日本語を日常的に話す私たちでさえ、言い回しに悩むことや、正しく敬語が使えているか迷うこともあるでしょう。
日本語には複雑な面がありますが、その分だけ多様な表現があるとも言えます。字のなりたちや意味、音訓の響きなどに味わいを見出すこともできます。
身近なところでは、私たちの名前も、漢字の意味やイメージ、画数、読み方、姓とのバランスなどを様々に考慮して名付けられたことでしょう。
辞書を調べれば、様々な発見があるでしょう。時には当たり前に話している日本語を謙虚に学び、親しんで、日々の生活を豊かにしたいものです。
今日の心がけ◆日本語に親しみましょう
出典:職場の教養4月号
感想
この文章には、日本語という言語の奥深さと美しさが、丁寧に描かれていると感じました。
特に、「複雑な面があるからこそ多様な表現ができる」という指摘には深く共感します。
日本語は、表音文字と表意文字を併せ持つ稀有な言語であり、その構造そのものが文化的な背景や美意識と深く結びついています。
漢字の成り立ちを調べたり、言葉の響きを味わったりする中で、日本語の豊かさを再発見できるという視点は、言葉に対する敬意と愛情を感じさせます。
また、日常的に使っている日本語であっても、「正しく敬語が使えているか迷うことがある」と認める謙虚さは、多くの日本人が共感できる実感だと思います。
そしてそれが「学ぶ姿勢」へと自然につながっていく流れには、言葉を通して人としての在り方を見つめ直すきっかけがあるように思えます。
「今日の心がけ」としての“日本語に親しむ”という提案も、堅苦しい学習ではなく、日々の暮らしの中で柔らかく取り入れられるアプローチで、心地よい余韻を残してくれます。
否定的な感想
この文章にはやや理想化された視点が強く、実際の日本語学習や運用の困難さへの具体的な配慮が少ないようにも感じました。
特に、外国人にとって日本語を学ぶハードルの高さは、表記体系の複雑さや敬語の使い分け以上に、非言語的な文脈の読み取りや曖昧な表現の多さにあります。
文章中では、日本語が難しいという前提は述べられていますが、その困難さがどれほど学習者の足かせになりうるかにはあまり踏み込まれていません。
また、「名前の付け方」に言及するくだりも、文化的には興味深い一方で、読者によっては少々話題が散漫に感じられるかもしれません。
名前の意味や画数にまで意識を向けることが“言葉を味わう”行為の一環として語られているものの、それが日本語の学びとどのように繋がるのかが少し曖昧です。
結果として、「親しむ」ことの意味がやや抽象的に響いてしまい、読者が具体的にどう行動すればいいのかというヒントが薄くなってしまっている印象も受けました。
感想がいまいちピンとこない方は…
「なんかしっくりこないんだよなぁ」「でもなかなか思いつかない…」そんな時は、感想文ジェネレーターをお試しください。
お好みのテイスト・文字数で感想を生成できます!